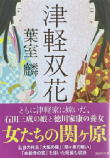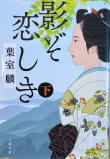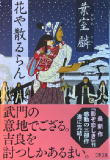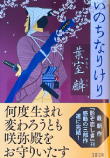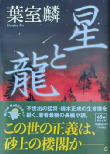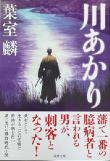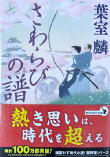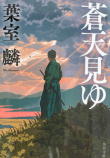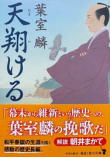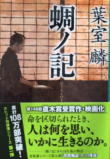昭和road
葉室麟おすすめ
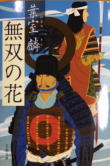 |
無双の花立花宗茂は大友宗麟臣下の実父高橋紹運、立花道雪の養子であり島津侵攻時に豊臣秀吉援軍時に島津勢を破り功を認められ豊臣臣下で大名となる。関ケ原の戦いでは西側について後に家康に認められ召し抱えられ旧領に復帰した唯一の武将の生涯を描いています。生涯自分の戦いで負け知らずな実直で正義感の塊、こんな武士らしい武士の立花宗茂を葉室さんが書くのですから愛さずにはいられません。 |
 |
冬姫信長が認めていた蒲生氏郷の正室になった冬姫は信長の実の娘で信長が最も愛した姫でもあった。生母をこの小説では終盤まで隠し、健気に芯をぶらさず信長と夫を支える姿勢の描写は読む人を魅了させる。葉室小説を次から次へと読み漁りたくなります。 |
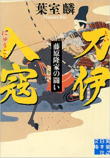 |
刀伊入寇武闘派の公卿藤原隆家が倭寇以前に対馬、壱岐、筑前(福岡)に侵攻した刀伊(夷狄)を迎撃する話です。著者ならではの主人公への思い入れは自分がその場にいるような錯覚を覚え臨場感を感じさせる読み応え大のおすすめ小説です。 |
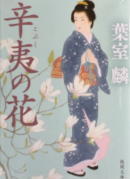 |
辛夷の花刀は二度と抜かないと誓い鍔と栗形を浅黄の紐で結んだ"抜かずの半五郎"が刀を抜く、抜かねば武士では無い、実にかっこいい、唯々かっこ良過ぎる。藩主のため、隣家の難事を救うため、いや密かに思う人のために。凛とした志桜里、その妹の婚約者幸四郎がまたかっこいい心が洗われる読後感がなんと気持ちの良いことか。 |
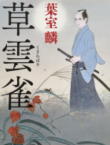 |
草雲雀忠臣をテーマに現世では考えられない実直な武士の生き様を書く著者には珍しく、今風に言えばちょっと女々しい剣客の妻への愛を剣によって貫く様を描いています。本の帯に"ひとはひとりでは生きていけませぬ"とあり、まさしく本書を言い現わしています。やはり期待をいつも裏切らぬ最後が用意されていて読後爽快感は毎度のことです。 |
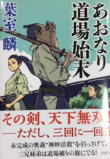 |
あおなり道場始末葉室小説には珍しく娯楽時代小説です。秘剣を取得している剣客が主人公であるがその秘剣は成功にむらがあったリでシリアスな話の中にコミカルなやりとりあり、ラブストーリーもあるという安心して最初から最後まで楽しめて読後は幸福感が残ります。 |